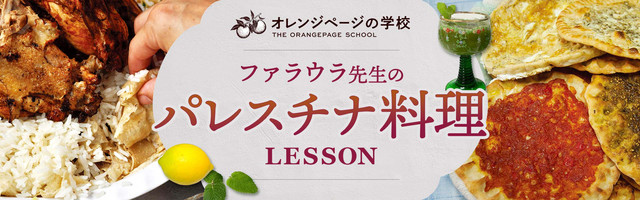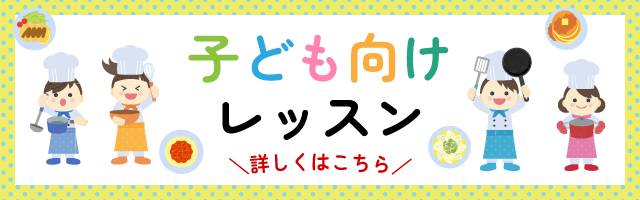いやさかクッキング
- フォロー
- 送る
- この教室へ問い合わせ
- 予約レッスン無し
- 山梨県
- の教室
料理に使うお塩はどれが良い?天日塩はほんものを選びましょう。
末木 弥栄子 先生のブログ 2021/7/7 22:21 UP
-
●料理に使うお塩はどれが良い?天日塩はほんものを選びましょう。
おいしい発酵食、菜食で
免疫力UP、デトックス!!
『山梨県』いやさかクッキング
末木 弥栄子(すえきやえこ)です。
少人数アットホームな教室ゆえに、
食のお悩みも、一緒に解決出来たらうれしいです!!
今日は天日塩の選び方のお話です。
「天日塩」・・・読み方は 、
・てんぴじお
・てんぴえん
・てんじつえん
といろいろありますが、言いやすいので大丈夫です。
「天日塩」と聞くと体に良さそう、というイメージがありますね。
実際に売り場で見ると、価格も様々な天日塩が並んでいます。
どれを選んだらいいの?と、考えてしまいますよね。
天日塩の製塩方法としては、
海水を塩田に引き込み、太陽熱と風力で天日干しして水分を蒸発させて作るやり方です。
雨が少なく乾燥した気候で、広い土地がある地域に多い製塩方法ということです。
パッケージの後ろ側を見ると、原材料は「海水」でどれも同じですが、
ほんものかどうか見分けるポイントは、
1 工程をチェックする。
「洗浄」「溶解」「イオン膜」「逆浸透膜」と書かれていないものを選ぶのが確実、と言われています。
・純粋な天日塩なら「天日 乾燥 粉砕」のみ記載。
・擬似天日塩なら「天日 溶解 乾燥 粉砕」、「天日 洗浄 乾燥 粉砕」「天日 イオン膜 乾燥 粉砕」など。
「天日 洗浄 乾燥 粉砕」とあるものは、天日塩を一度飽和食塩水に溶かし込んで洗浄しているということです。
その後の乾燥は天日(太陽熱)であるはずもなく、
含まれていたミネラル等のにがり成分は流れて消えてしまい、
そのため、後から色付けしたりミネラルを添加しているタイプもあります。
2 成分の記載が「塩化ナトリウム99%以上」なら精製塩(いわゆる化学塩)と変わらない。
未精製のものは、塩化ナトリウムはもっと少ないはずです。
以上の2点がチェックすべき項目です。
行程と成分を見て、
「工程」自体表示されてない物は、パッケージに良さそうなことが書かれていても、疑似品の可能性が高いかも知れません。
わたしがお伝えする穀物菜食では、お塩の質をとても大事に考えています。
いやさかクッキングで使っているのは「カンホアの塩」です。
お料理にも、お味噌や梅干し仕込みにも、パンやお菓子に使うのも、カンホアで統一しています。
また、同じ塩を、お鍋で煎って焼き塩も作っています。
焼き塩は主におむすびに使っています。
お塩をいいものに変えるだけで、お料理の味がグンと良くなります。
おいしくてミネラル成分も摂れて体調も整える、って、
良いお塩というのはほんとうに素晴らしいですね。
それは、生徒さんたちもよくお分かりで、
価格は500gで500円と買いやすいお値段なこともあり、カンホアの塩を買って帰られる方が多いです。
【カンホアの塩の広告サイトから】
海水は多種多様の成分(無機質)を含んでいるため、その味はいたって複雑です。
海水をなめると、単に塩辛いだけではなく、何とも言えぬ味がするのはそのため。
カンホアの塩は、独自の天日製法によって、海水の様々な成分を『全体的に』取り込み、『海のような、深く豊かな味わい』を作り上げています。
カンホアの塩の味を作っているのは、ナトリウムだけでなく、マグネシウム・カルシウム・カリウムを始めとした海水の様々な成分です。それらをこの専用の塩田で調えながらカンホアの塩は作られています。
例えば、その味の中に、ほのかな甘みと独特のうま味があります。
「甘み・うま味」とはいうものの、海水には糖分やうま味成分はありません。
それらは海水の様々な成分の様々な味が(複合的に)織りなされることで、醸し出されています。
そしてそれが料理・素材の味を包み込むように引き立てます。
(↑転載は以上)
↓ よいお塩は塩壺に入れておくと、さらにエネルギー高くなりますよ~。
長年愛用の塩壺たち。
三重県の陶芸家 榎本合歓さん作。
クッキング入門 日程と内容はこちら♥
《教室へのお問合わせ、申込み》
お問合わせフォームはこちら♥
090-3630-2662
yaekonana@yahoo.co.jp
アクセス:JR身延線 小井川駅徒歩8分/駐車可
受付時間
携帯電話(休日もOK) 8時~21時
メールは24時間受信OK。
公式LINEが出来ました♪
まだまだ使い慣れていませんが、もしよかったら↓
先生情報 |
|
 |
末木 弥栄子 |
|
穀物菜食の教室を始めて18年。 子どもの体質改善目的で、独学でマクロビオティックを実践したことが始まり。 穀物菜食、雑穀料理、酵素玄米、重ね煮、手当法などを学び、伝え、探究する日々。 息子三人が全員成人し、夫婦だけの落ち着いた暮らしの中で教室を続けています。 2008年「未来食つぶつぶ」初のインストラクター取得。 プロフィール詳細をみる |
|