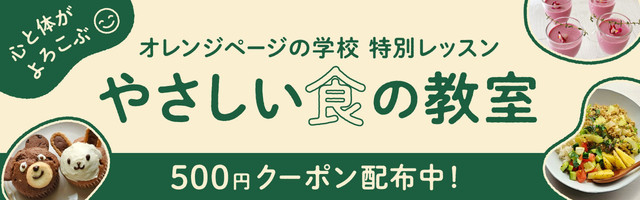ロイヤル・プリンセス・スタイル
- フォロー
- 送る
- この教室へ問い合わせ
- 予約レッスン無し
茶花とは?茶道で飾られるお花ってどんなお花?
竹田理絵 先生のブログ 2020/5/9 15:42 UP
-
こんにちは。茶道体験の銀座 茶禅です。
今日は5月9日。 二十四節気の「立夏」、七十二候の「初候 蛙始鳴(かえるはじめてなく)」にあたります。
今日は茶室で飾られる花について、ご紹介したいと思います。
茶道では、亭主がその日の茶会に対する想いを込めて掛け軸を選び花を生けます。
そして、茶席を彩るお道具やお抹茶とは異なり、唯一「命」があるお花。
季節を表すだけでなく、同じ花には二度と会えない、まさに一期一会の大切な役割を果たしているのです。
大きな役割がある茶花にはいくつかの決まり事がありますが、それらを知ることでよりお茶席が楽しいものになっていきます。
茶花について季節のお花と共にご紹介して参ります。
5月の茶花、白撫子。織部焼の花入れで。
茶花とは
茶道でお茶室の床の間に生ける花のことを茶花といいます。
千利休の教えでは「花は野にあるように」とあります。
即ち、フラワーアレンジメントのように美しく盛り付けるものではなく、まるで自然の中に咲いているような花本来のありのままの姿を表現するため、「投げ入れ」という様式で生けるのが原則とされています。
投げ入れには華道と違って型はなく、予め頃合いに切った花を手で一度に花入れに入れます。このように、花を「入れる」という表現を茶道では使います。
咲き誇る花よりも、控えめな蕾の状態のものを使います。
亭主は、その日のお茶会の趣向やお茶席の雰囲気に調和し、かつ旬の季節感を茶室に表現するために茶花を選びます。
招かれたお客様は、その季節感あふれた自然な美を楽しみ、亭主の心づかいに感謝し、同時に命や時の流れを感じていきます。
茶道の季節と茶花
茶道では季節を11月から4月の「炉」と5月から10月の「風炉」に分けています。
茶花自体は季節により様々な種類が用いられますが、
炉と風炉の季節に合わせて花を生ける花入れや、代表的な花が変わります。
炉の季節 11月~4月
曙椿と照り葉
鶴首型などの細い花入れでバランス良く
炉の季節に使われる茶花で最も好まれるのは椿(つばき)です。
椿は冬の寒さに耐えながら咲く、茶席に拘わらずその美しさと上品さが多くの人に愛されている花ですね。
椿にも数千種類あると言われていますが、茶花で良く使われるのは、小ぶりな「侘助」やすこしふっくらした「白玉椿」などです。名前も風情があると思いませんか?
また、初冬では、椿と一緒に「照り葉」と呼ばれる紅葉した木の葉を添えることもあります。ハシバミや万作がよく用いられます。
花入れには素朴な美しさのある備前焼や信楽焼、竹のものが椿と相性が良く多用されます。
2月になると梅や節分草、3月は福寿草や白木蓮、4月は牡丹や山吹などを生けます。
風炉の季節 5月~10月
夏花と吾亦紅。
花入れは槍の鞘の形をしていることから「さや籠」
置き型ではなく掛け花で。
新緑がまぶしい初夏から暑い真夏を経て紅葉に向かう秋となる、草花の季節の移り変わりを楽しむ風炉季節には、まさに利休の「花は野にあるように」、様々な花だけでなく葉や草も茶花として多用されます。
風炉の季節に使われる茶花で最も好まれるのは木槿(むくげ)です、
夏の暑さの中で咲く「涼やかさ」、一日だけしか咲かないという「はかなさ」はまさに一期一会の精神を表しており、昔から茶人に好まれてきました。
5月:檜扇、芍薬、アザミ、蛍袋、なでしこ、藤 など
6月:山紫陽花、鉄仙、釣船草 など
7月:桔梗、ヒメジョオン、朝顔、半夏生 など
8月:ほおずき、撫子、姫ひまわり など
9月:秋明菊、芙蓉、藤袴、吾亦紅 など
10月:風炉の最後の月でその名残を惜しみます。秋の名残の花を沢山生けても良いことになっています。
花入れには籠を使うのが主流です。
茶席に相応しくない=禁花
自然の中に咲く花の中でも茶席にふさわしくないとされる花もあります。
安土桃山時代に千利休の茶の心得や秘伝などを書き留めた『南坊禄』という茶道書に、禁花について書かれています。
---------
茶花に生けぬ花、狂歌に花入れに入れざるは沈丁花
太山しきみに鶏頭の花
女郎花ざくろ河骨金銭花
せんれい花も嫌いけりなり
---------
これを読み解くと禁花の考え方が分かります。
香りの強い花
茶席では炉や風炉の中でお香を焚きます。お香の香りとぶつかる香りの強い花は好まれません。
沈丁花(ちんちょうげ)、百合、薔薇、梔子(くちなし)、金木犀(きんもくせい)など
毒、とげのある花
太山きしみ(たやまきしみ)は毒があるとか、鶏頭(けいとう)はその見た目が毒々しいということで扱いづらいため使われません。
同じ理由で薔薇のようなとげのあるものも好まれません。
個人的には鶏頭が野に咲いている様子は美しいと思うのですけどね 笑
名前の悪いもの
女郎花(おみなえし)の「女郎」という名前によるものです。
河骨(かうほね)の「骨」も同様です。
先に挙げた梔子も「死人にくちなし」の語が使われるため名前が悪いとされています。
実が主役の花
ざくろやみかん、栗など。見どころが無い ということでしょうか。
季節の無い花
金銭花(きんせんか)のように四季を通して咲く花は、季節感を大事にしている茶道には向かないということでしょう。
最後のせんれい花については、様々な著書でも不明とされています。。。
但し、例えば女郎花はおみなえしと読み、女郎のイメージではないので現代では使われるなど、時代とともに禁花に対する考え方も変わってきているようです。
茶花はどこで購入できる?
街の花屋さんでは残念ながらなかなか茶花を手に入れることはできません。
東京で茶花のお店として有名な2店舗をご紹介します。
立ち寄られるだけで茶道の風情を感じることができますよ。
1.青山 「花長」
公式サイトは今のところ無いようです。
表参道駅と広尾駅のちょうど中間のあたりにあります。
茶道をある程度たしなんでいる方はほぼ皆さん訪れたことのあるお店といってよいでしょう。
2.銀座「野の花 司」
松屋銀座のすぐ裏にあります。お店の外に沢山ディスプレイされているので眺めやすいですね。
野の花 司 サイトへ
以上、今日は茶室に飾る花について、ご紹介しました。
是非お茶室でお茶をいただきながら、自然美を感じてみてください。
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
「今は自粛でまだ行けないけど、行けるようになったら行きたい!」
と応援してくださる皆様に、感謝を込めた先行予約キャンペーンです。
先行予約に限り、特別限定価格でご提供させていただきます。
先生情報 |
|
 |
竹田理絵 |
|
おもてなしや茶道を通じて日本の伝統文化の素晴らしさをお伝えしたいという思いから、本格的で本物、それでいて敷居を低くした茶道体験やおもてなしセミナーを展開しています。 フランスの凱旋門やニューヨークのタイムズスクエアなど、海外の路上でお茶会を開くという、ユニークな形で日本のおもてなしや茶道を世界中に広めています。 プロフィール詳細をみる |
|